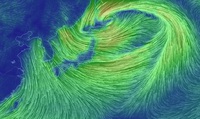2010年01月13日
私たちに今必要なこと
「誰がこの子らを救うのか?」
~今、子ども達に起こっている現状と課題~
2010年1月9日土曜日。
今年一発目の参加したシンポジウムはこれだ。
去年、うるま市で起こった中学生による殺傷事件を受けて、このシンポジウムがうるま市市民芸術劇場で行われた。
14時からシンポジウムは開演。
シンポジウムのコーディネーターを務めていたのは、
沖縄大学教授の加藤彰彦さん。
パネリストは
垣花 鷹志さん(元那覇保護観察所所長)
河上 親彦さん(北谷町青少年支援センター所長、主任児童員)
崎原 林子さん(臨床心理士、スクールカウンセラー)
冨底 正得さん(前北谷町立桑江中学校校長、嘉手納町教育委員会教育指導課長)
山内 優子さん(元コザ児童相談所所長)
以上の5名。
シンポジウムは私の都合上最後までは参加することはできなかったが、途中まで参加しての感じたことを書いていきたいと思う。
中学生による殺人。
少しでもよりよい社会・子どもたちが健全に育っていく環境をつくっていくために、私たちはこの現実を強く受け止め、すぐにでも行動に移していかなければいけないと思う。
それを考えていく上にあたって、以前から私が思っていたことがある。
いじめの発生件数は近年減少しているが、その数値とは裏腹に児童生徒にまつわる事件は増えているのが現実だ。
その原因として考えられるのが2点ある。
それは、いじめの陰湿化と子どもたちの育つ環境の劣悪化だと私は思う。
特に子どもたちの育つ環境の劣悪化が一番の原因だ。
まず、いじめの陰湿化について述べる前に、いじめについて少しふれておきたい。
いじめという行為自体は発達段階で起こる行為のひとつだ。
中学生にいじめが多い原因は発達段階にある。中学生ぐらいになると性への目覚めにより、自我意識が芽生え始める。自我意識が芽生えるということは周りの目を気にし始めるのがこの頃だ。
自分の中学校時代を振り返ってほしい。
ファッションや化粧、髪型などに興味を持ち始めるのは中学生(女の子は小学生から持ち始めている子もいる)頃ではなかっただろうか。
そうやって周りの目を気にし始める頃、仲間意識が極度に強くなる。
排他的な遊び仲間を作りだすのもこの頃である。
まさにギャングエイジの時期である。
ギャングエイジはその名の通り、ギャングのような世代のことを指す。
この世代の友人関係は、他の世代を寄せ付けない。また、同世代でも特に認めた相手にしか友人関係をつくらない。場合によっては儀式的なことを行い、集団のために自己犠牲的なことを要求される。
いじめは、この発達段階における代表的な行動、いってしまえば当たり前の行動でもあるのだ。
最近、そのいじめは陰湿化してきていると私は思う。
その理由の一つが、パソコンや携帯電話といったコミュニケーションツールが増えたことだ。TVでもたまに報道されるが、ネット上の掲示板に「○○死ね」とか「○○ムカツク」などの暴言が数えきれないほど書かれてしまったり、携帯メールで暴言を言われたりして自殺に追いやられる事件が起こっている。
また、携帯電話を使うと教師や保護者が気付かないようにメールや電話で呼び出して暴行を加えるなど容易なことだ。場合によっては同世代の友達でさえ気づかないかもしれない。
こういったことを考えると、
今の世の中は、いじめが陰湿化しやすい。
そして、それに加え、子どもたちの育つ環境にも問題がある。
先程、いじめが陰湿化して見えにくくなっていると言ったが、追い打ちをかけるように、私たちが子どもたちをしっかり見ていないという現状がある。
その証拠に、
あなたは近所の子どもの名前を何人知っているでしょうか?
ほとんどの子どもたちを知っているという人は、果たしてこの日本に何人いるだろうか。
偉そうにこんなブログを書いている私も近所の子のことはほとんど知らない。
これが現状である。
地域の子どもを知らない。何か問題が起こっていても、私たちは子どもたちを見ていないから問題はどんどんエスカレートするのだろう。公の場で出てくる頃には問題はかなり大きくなってしまって、取り返しのつかないことになる。
シンポジウムでは、沖縄の貧困が子どもたちを育てる環境をつくれてないという話題も出た。確かに間違ってはいないと思う。沖縄が全国に比べて所得が低く、離婚率も高いことは以前から問題になっていることだ。
しかし、思い出してみてほしい、
これまで沖縄の人は貧困の中でもしっかりと支えあって生きてきたはずだ。
あんな悲惨な戦争があっても、まだ沖縄の温かい人たちは残っている。そういうオジィやオバァがガタガタになった沖縄を支え、立て直していったのだ。
皆が支えあったからこそ、今の沖縄があるのだと私は思う。
その時代を生き抜いたオジィ・オバァは近所の人のことを本当によく知っている。親戚でもないのに近所のこどもの年齢まで把握していることも珍しくはない。
これは、地域で支えあい、地域に目を向けてきた証拠だ。
だからこそ、今、人の支えあいや地域に目を向けることを忘れてはいけないと思ってやまない。
ガタガタな社会になっているときだからこそ、支えあう必要がある。
国の政策や県行政の対応を待っている&期待していても、この問題は解決しない。むしろ悪化していくような気もする。
まさに、事件は会議室で起こってるんじゃない、現場で起きてるんだ。
うるま市で起こった中学生による殺傷事件。
この問題はとても大きく複雑な問題に感じるが、何も難しいことを考える必要はない。昔の沖縄の地域で支えあう姿に戻るのが一番の解決法だと思う。そのためにも、まずは近所の家の子どもを知る・目を向けること、まずはこの一歩から始めることが今の私たち大人にとって重要なことではないだろうか。
~今、子ども達に起こっている現状と課題~
2010年1月9日土曜日。
今年一発目の参加したシンポジウムはこれだ。
去年、うるま市で起こった中学生による殺傷事件を受けて、このシンポジウムがうるま市市民芸術劇場で行われた。
14時からシンポジウムは開演。
シンポジウムのコーディネーターを務めていたのは、
沖縄大学教授の加藤彰彦さん。
パネリストは
垣花 鷹志さん(元那覇保護観察所所長)
河上 親彦さん(北谷町青少年支援センター所長、主任児童員)
崎原 林子さん(臨床心理士、スクールカウンセラー)
冨底 正得さん(前北谷町立桑江中学校校長、嘉手納町教育委員会教育指導課長)
山内 優子さん(元コザ児童相談所所長)
以上の5名。
シンポジウムは私の都合上最後までは参加することはできなかったが、途中まで参加しての感じたことを書いていきたいと思う。
中学生による殺人。
少しでもよりよい社会・子どもたちが健全に育っていく環境をつくっていくために、私たちはこの現実を強く受け止め、すぐにでも行動に移していかなければいけないと思う。
それを考えていく上にあたって、以前から私が思っていたことがある。
いじめの発生件数は近年減少しているが、その数値とは裏腹に児童生徒にまつわる事件は増えているのが現実だ。
その原因として考えられるのが2点ある。
それは、いじめの陰湿化と子どもたちの育つ環境の劣悪化だと私は思う。
特に子どもたちの育つ環境の劣悪化が一番の原因だ。
まず、いじめの陰湿化について述べる前に、いじめについて少しふれておきたい。
いじめという行為自体は発達段階で起こる行為のひとつだ。
中学生にいじめが多い原因は発達段階にある。中学生ぐらいになると性への目覚めにより、自我意識が芽生え始める。自我意識が芽生えるということは周りの目を気にし始めるのがこの頃だ。
自分の中学校時代を振り返ってほしい。
ファッションや化粧、髪型などに興味を持ち始めるのは中学生(女の子は小学生から持ち始めている子もいる)頃ではなかっただろうか。
そうやって周りの目を気にし始める頃、仲間意識が極度に強くなる。
排他的な遊び仲間を作りだすのもこの頃である。
まさにギャングエイジの時期である。
ギャングエイジはその名の通り、ギャングのような世代のことを指す。
この世代の友人関係は、他の世代を寄せ付けない。また、同世代でも特に認めた相手にしか友人関係をつくらない。場合によっては儀式的なことを行い、集団のために自己犠牲的なことを要求される。
いじめは、この発達段階における代表的な行動、いってしまえば当たり前の行動でもあるのだ。
最近、そのいじめは陰湿化してきていると私は思う。
その理由の一つが、パソコンや携帯電話といったコミュニケーションツールが増えたことだ。TVでもたまに報道されるが、ネット上の掲示板に「○○死ね」とか「○○ムカツク」などの暴言が数えきれないほど書かれてしまったり、携帯メールで暴言を言われたりして自殺に追いやられる事件が起こっている。
また、携帯電話を使うと教師や保護者が気付かないようにメールや電話で呼び出して暴行を加えるなど容易なことだ。場合によっては同世代の友達でさえ気づかないかもしれない。
こういったことを考えると、
今の世の中は、いじめが陰湿化しやすい。
そして、それに加え、子どもたちの育つ環境にも問題がある。
先程、いじめが陰湿化して見えにくくなっていると言ったが、追い打ちをかけるように、私たちが子どもたちをしっかり見ていないという現状がある。
その証拠に、
あなたは近所の子どもの名前を何人知っているでしょうか?
ほとんどの子どもたちを知っているという人は、果たしてこの日本に何人いるだろうか。
偉そうにこんなブログを書いている私も近所の子のことはほとんど知らない。
これが現状である。
地域の子どもを知らない。何か問題が起こっていても、私たちは子どもたちを見ていないから問題はどんどんエスカレートするのだろう。公の場で出てくる頃には問題はかなり大きくなってしまって、取り返しのつかないことになる。
シンポジウムでは、沖縄の貧困が子どもたちを育てる環境をつくれてないという話題も出た。確かに間違ってはいないと思う。沖縄が全国に比べて所得が低く、離婚率も高いことは以前から問題になっていることだ。
しかし、思い出してみてほしい、
これまで沖縄の人は貧困の中でもしっかりと支えあって生きてきたはずだ。
あんな悲惨な戦争があっても、まだ沖縄の温かい人たちは残っている。そういうオジィやオバァがガタガタになった沖縄を支え、立て直していったのだ。
皆が支えあったからこそ、今の沖縄があるのだと私は思う。
その時代を生き抜いたオジィ・オバァは近所の人のことを本当によく知っている。親戚でもないのに近所のこどもの年齢まで把握していることも珍しくはない。
これは、地域で支えあい、地域に目を向けてきた証拠だ。
だからこそ、今、人の支えあいや地域に目を向けることを忘れてはいけないと思ってやまない。
ガタガタな社会になっているときだからこそ、支えあう必要がある。
国の政策や県行政の対応を待っている&期待していても、この問題は解決しない。むしろ悪化していくような気もする。
まさに、事件は会議室で起こってるんじゃない、現場で起きてるんだ。
うるま市で起こった中学生による殺傷事件。
この問題はとても大きく複雑な問題に感じるが、何も難しいことを考える必要はない。昔の沖縄の地域で支えあう姿に戻るのが一番の解決法だと思う。そのためにも、まずは近所の家の子どもを知る・目を向けること、まずはこの一歩から始めることが今の私たち大人にとって重要なことではないだろうか。
Posted by Cinnamomum_mk at 18:20│Comments(0)
│活動