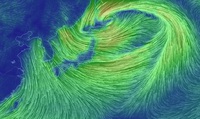2010年11月18日
勉強って?
こんばんは。
長らく更新していなかったので、
なかなかログインできずにいました。笑
最近、気になるワードがあります。
「ごまかし勉強」って聞いたことありますか?
最近、ちょこっと本で読んだんですけど。。。
私にとっては、
あぁ、高校・大学受験の時はまさにこれだったなぁと感じるものでした。
「ごまかし勉強」の説明を本から引用してみました。
「ごまかし勉強」(藤沢2002)
目先の定期試験を乗り切るだけの目的で行う手抜き勉強のこと。
試験に出ないところは割愛し、他人の作った要点集や暗記材料を
意味も考えずに機械的に暗記し、学習方略を工夫せずに反復練習の量だけを増やし、
思考力よりも結果を重視するような勉強のやり方を指す。
学習者の認知システムの中に意味ネットワークが形成されないために、
試験が終われば学習内容は忘れてしまう。ごまかしに成功した場合は、
内容の面白さや知的成長が実感できないので、学習労役感が形成され、
学習や授業の価値が低下する。
うーん…
私の中では“手抜き”という言葉に少しひっかかりはあるものの、
まさに大学受験の時の勉強方法はこれであったなと思った。
私は高校3年生の5ヶ月間程度塾に通っていて、
そこでは大学合格という目的を達成するために、
ひたすら問題を解いて、暗記しての反復だった。
塾の講師からは「大学受験なんて暗記テストみたいなもの」と言われて、
ただただテキストにある内容やテストで解けなかった問題の解き方などを
暗記していく(暗記方法に違いはあるものの)だけの勉強が続いた。
しかし、私の場合、高校時代さほど偏差値も高くなく、
浪人をしてまで大学に行ける環境にいるわけでもなかったので、
短期で結果を出すには、この「ごまかし勉強」は良かったと思う。
確かに、
藤沢さんの言うように学習者の認知システムの中に
意味ネットワークが形成されてないためか、
大学受験が終わってある程度の時間が経ってしまうと、
恐ろしい程にその学習内容の大部分を忘れてしまっていた。
大学1年生のはじめの頃は、あんなに大変な思いをして詰め込んだ知識を、
いとも簡単に忘れてしまうなんて、
脳に障害でもあるではないだろうかと思ってしまうこともあったが、
今「ごまかし勉強」について学んで納得。
しかし、よく考えてみると、
今の子ども達の学習環境はこの「ごまかし勉強」を助長するものではないかと思う。
その一つとなるものが定期試験や
その他単元テストなどによる評価方法ではないだろうか。
子どもたちはある程度の年齢までくると、
テストで良い点数を取らなければ成績に響くことを経験的に知っている。
良い成績を取らなければ親や先生達から「もっと勉強しなさい」とか
「もっと頑張りなさい」など叱責を受けることになる。
さらには良い成績を取らなければ良い高校や大学に進学できないと言われ、
良い高校・大学とはどんな学校なのかよく分からないまま子どもたちは、
良いとされるものを目指し勉強を頑張る。
テストの点数を確実に上げていくには、
授業の中で「テストに出る」と言われたところを重点的に
テスト範囲の内容をひたすら暗記。
テストのほとんどが知識を問うような問題なので、
これが一番効率よく点数が取れる。
しかし、学校の授業についていける子どもはこれでよいが、
それだけではついていけない子どもにとってはかなり大変なことである。
そして、その子ども達の助け船のように現れたのが学習塾。
これが「ごまかし勉強」を助長するもう一つの要因である。
学校のテストや受験の点数を取るためのスキルを学べるために、
個人差はあるものの確実に結果はついてくる。
こうやって全体が底上げされることによって、良い成績をとることや、
受験に合格することに対して「競争」が白熱化していく。
この競争の白熱は「ごまかし勉強」に拍車をかけ、
今の子ども達に取り巻く今の学習環境を形成していったのではないだろうかと私は思う。
しかし、
この「ごまかし勉強」は高度経済成長期の日本には通用していたのではないだろうか。
その当時は成長していく経済には、
とにかく一定の知識・技能を身につけている人材・労働力が求められていたと聞く。
また、その中でも勉強をして成績をあげ、偏差値の高い高校、
そして大学に進学することができれば、卒業後は待遇の良い職業に就くことができ、
明るい未来が約束されていた。みんな明るい未来を求めて、
学習や授業の価値が低いと言われている「ごまかし勉強」でも頑張って勉強していた。
しかしバブル崩壊後、日本経済は低迷し失業者も増え、
偏差値の高い大学に進学しても明るい未来は保障されないのが現状。
今の社会ではある一定の知識・技能をもつ人材ではなく、
今までの知識・技能を応用して新しい物や価値観、そして産業を作り出し、
日本経済を引っ張っていく人材を求めているから、
ただ知識を詰め込んでいく「ごまかし勉強」のようなものは
ダメとされるようになってきたように感じる。
だが、その当時、とにかく偏差値の高い学校に進学することを
良しされて育ってきた子どもたちは、今の大学生や高校生、
場合によっては小・中学生を育てる親になっている。
その親たちは自分たちが育ってきたように今の子どもたちに教育し、
高い偏差値を求めて勉強させる。学校の評価の方法や受験システムも
なかなか変わらないので、「ごまかし勉強」は生き続ける。
また、さらに、近年は子も達の「学力低下」問題が「ごまかし勉強」に拍車をかける。
学力テスト最下位県の沖縄では学校行事を削減して授業時数を増やす市町村もある。
偏差値の高い高校・大学に進学すると明るい未来が待っているという構図は
すでに崩壊しているのに、「ごまかし勉強」は生き続ける。
そういった意味では、今の子どもたちは勉強するということが
とても苦痛になっているような気がしてやまない。PISA調査で日本が
学習習慣や学習意欲に対して課題があると指摘されたのも頷けるような気がする。
高い偏差値を目指すことだけが子ども達の将来に直結しにくくなった今、
これからは学校やその他社会で勉強する・学ぶことの意味をそれぞれで模索し、
それを子ども達に伝え・実感させていくことが必要ではないだろうかと思う今日この頃。
書きすぎました 笑
極端に書いたので、不快な思いをさせてしまった人がいたらごめんなさい。
長らく更新していなかったので、
なかなかログインできずにいました。笑
最近、気になるワードがあります。
「ごまかし勉強」って聞いたことありますか?
最近、ちょこっと本で読んだんですけど。。。
私にとっては、
あぁ、高校・大学受験の時はまさにこれだったなぁと感じるものでした。
「ごまかし勉強」の説明を本から引用してみました。
「ごまかし勉強」(藤沢2002)
目先の定期試験を乗り切るだけの目的で行う手抜き勉強のこと。
試験に出ないところは割愛し、他人の作った要点集や暗記材料を
意味も考えずに機械的に暗記し、学習方略を工夫せずに反復練習の量だけを増やし、
思考力よりも結果を重視するような勉強のやり方を指す。
学習者の認知システムの中に意味ネットワークが形成されないために、
試験が終われば学習内容は忘れてしまう。ごまかしに成功した場合は、
内容の面白さや知的成長が実感できないので、学習労役感が形成され、
学習や授業の価値が低下する。
うーん…
私の中では“手抜き”という言葉に少しひっかかりはあるものの、
まさに大学受験の時の勉強方法はこれであったなと思った。
私は高校3年生の5ヶ月間程度塾に通っていて、
そこでは大学合格という目的を達成するために、
ひたすら問題を解いて、暗記しての反復だった。
塾の講師からは「大学受験なんて暗記テストみたいなもの」と言われて、
ただただテキストにある内容やテストで解けなかった問題の解き方などを
暗記していく(暗記方法に違いはあるものの)だけの勉強が続いた。
しかし、私の場合、高校時代さほど偏差値も高くなく、
浪人をしてまで大学に行ける環境にいるわけでもなかったので、
短期で結果を出すには、この「ごまかし勉強」は良かったと思う。
確かに、
藤沢さんの言うように学習者の認知システムの中に
意味ネットワークが形成されてないためか、
大学受験が終わってある程度の時間が経ってしまうと、
恐ろしい程にその学習内容の大部分を忘れてしまっていた。
大学1年生のはじめの頃は、あんなに大変な思いをして詰め込んだ知識を、
いとも簡単に忘れてしまうなんて、
脳に障害でもあるではないだろうかと思ってしまうこともあったが、
今「ごまかし勉強」について学んで納得。
しかし、よく考えてみると、
今の子ども達の学習環境はこの「ごまかし勉強」を助長するものではないかと思う。
その一つとなるものが定期試験や
その他単元テストなどによる評価方法ではないだろうか。
子どもたちはある程度の年齢までくると、
テストで良い点数を取らなければ成績に響くことを経験的に知っている。
良い成績を取らなければ親や先生達から「もっと勉強しなさい」とか
「もっと頑張りなさい」など叱責を受けることになる。
さらには良い成績を取らなければ良い高校や大学に進学できないと言われ、
良い高校・大学とはどんな学校なのかよく分からないまま子どもたちは、
良いとされるものを目指し勉強を頑張る。
テストの点数を確実に上げていくには、
授業の中で「テストに出る」と言われたところを重点的に
テスト範囲の内容をひたすら暗記。
テストのほとんどが知識を問うような問題なので、
これが一番効率よく点数が取れる。
しかし、学校の授業についていける子どもはこれでよいが、
それだけではついていけない子どもにとってはかなり大変なことである。
そして、その子ども達の助け船のように現れたのが学習塾。
これが「ごまかし勉強」を助長するもう一つの要因である。
学校のテストや受験の点数を取るためのスキルを学べるために、
個人差はあるものの確実に結果はついてくる。
こうやって全体が底上げされることによって、良い成績をとることや、
受験に合格することに対して「競争」が白熱化していく。
この競争の白熱は「ごまかし勉強」に拍車をかけ、
今の子ども達に取り巻く今の学習環境を形成していったのではないだろうかと私は思う。
しかし、
この「ごまかし勉強」は高度経済成長期の日本には通用していたのではないだろうか。
その当時は成長していく経済には、
とにかく一定の知識・技能を身につけている人材・労働力が求められていたと聞く。
また、その中でも勉強をして成績をあげ、偏差値の高い高校、
そして大学に進学することができれば、卒業後は待遇の良い職業に就くことができ、
明るい未来が約束されていた。みんな明るい未来を求めて、
学習や授業の価値が低いと言われている「ごまかし勉強」でも頑張って勉強していた。
しかしバブル崩壊後、日本経済は低迷し失業者も増え、
偏差値の高い大学に進学しても明るい未来は保障されないのが現状。
今の社会ではある一定の知識・技能をもつ人材ではなく、
今までの知識・技能を応用して新しい物や価値観、そして産業を作り出し、
日本経済を引っ張っていく人材を求めているから、
ただ知識を詰め込んでいく「ごまかし勉強」のようなものは
ダメとされるようになってきたように感じる。
だが、その当時、とにかく偏差値の高い学校に進学することを
良しされて育ってきた子どもたちは、今の大学生や高校生、
場合によっては小・中学生を育てる親になっている。
その親たちは自分たちが育ってきたように今の子どもたちに教育し、
高い偏差値を求めて勉強させる。学校の評価の方法や受験システムも
なかなか変わらないので、「ごまかし勉強」は生き続ける。
また、さらに、近年は子も達の「学力低下」問題が「ごまかし勉強」に拍車をかける。
学力テスト最下位県の沖縄では学校行事を削減して授業時数を増やす市町村もある。
偏差値の高い高校・大学に進学すると明るい未来が待っているという構図は
すでに崩壊しているのに、「ごまかし勉強」は生き続ける。
そういった意味では、今の子どもたちは勉強するということが
とても苦痛になっているような気がしてやまない。PISA調査で日本が
学習習慣や学習意欲に対して課題があると指摘されたのも頷けるような気がする。
高い偏差値を目指すことだけが子ども達の将来に直結しにくくなった今、
これからは学校やその他社会で勉強する・学ぶことの意味をそれぞれで模索し、
それを子ども達に伝え・実感させていくことが必要ではないだろうかと思う今日この頃。
書きすぎました 笑
極端に書いたので、不快な思いをさせてしまった人がいたらごめんなさい。
Posted by Cinnamomum_mk at 22:40│Comments(3)
│活動
この記事へのコメント
沖縄で子育てをしているお父さん、お母さん
そして先生たちにお聞きしたいことがあります。
沖教組の先生たちは、盗人のようにこそこそ隠れて選挙活動の手伝いなどしていて、恥ずかしくないのでしょうか。
子供達は見ています。平気で法律を犯す、そのような姿を。その後ろ姿をこそ見ているのです。
中国は尖閣諸島の次は、沖縄本島を狙っています。
中国の脅威が目の前まで迫っているこの状況で、基地は県外? 正気ですか?
基地が県外に移設されれば、中国は喜んであっという間に沖縄を属領化するでしょう。
沖縄の先生たちが一生懸命、「基地は県外へ」と選挙活動をすることで
この沖縄は再び戦争の脅威にさらされるのです。
子どもたちに「平和教育」「命どぅ宝」と教えておきながら、
良心の呵責を感じないのでしょうか?
平和教育は、戦争を防ぐことを目的としているのでしょう。
中国の支配を受ければ、私たち沖縄県民は、沖縄戦以上の辛酸を舐め続けること
になることを想像してみてください。過去は変えられないが、未来は変えられる
ということを知ってほしいと思います。
そして先生たちにお聞きしたいことがあります。
沖教組の先生たちは、盗人のようにこそこそ隠れて選挙活動の手伝いなどしていて、恥ずかしくないのでしょうか。
子供達は見ています。平気で法律を犯す、そのような姿を。その後ろ姿をこそ見ているのです。
中国は尖閣諸島の次は、沖縄本島を狙っています。
中国の脅威が目の前まで迫っているこの状況で、基地は県外? 正気ですか?
基地が県外に移設されれば、中国は喜んであっという間に沖縄を属領化するでしょう。
沖縄の先生たちが一生懸命、「基地は県外へ」と選挙活動をすることで
この沖縄は再び戦争の脅威にさらされるのです。
子どもたちに「平和教育」「命どぅ宝」と教えておきながら、
良心の呵責を感じないのでしょうか?
平和教育は、戦争を防ぐことを目的としているのでしょう。
中国の支配を受ければ、私たち沖縄県民は、沖縄戦以上の辛酸を舐め続けること
になることを想像してみてください。過去は変えられないが、未来は変えられる
ということを知ってほしいと思います。
Posted by goya at 2010年11月20日 17:27
認知システムの中への意味ネットワークを形成しなくても、資格や手続きを取れば、教師や塾講師などの教える立場に立てる事が、ごまかしの始まりなのかもしれません。
だれでも、セミナー開ける時代ですからね〜、学習者側の知恵が必要です。
また、学校でさえノルマの宿題を与えて、ごまかし勉強になりつつあるのだから、そこを補う場も必要ではないか?というのが、私の学習塾設立の動機でもあります。
まずは、指導者のごまかし勉強からのリハビリを検討しては?
私もぜひリハビリしたいです。
だれでも、セミナー開ける時代ですからね〜、学習者側の知恵が必要です。
また、学校でさえノルマの宿題を与えて、ごまかし勉強になりつつあるのだから、そこを補う場も必要ではないか?というのが、私の学習塾設立の動機でもあります。
まずは、指導者のごまかし勉強からのリハビリを検討しては?
私もぜひリハビリしたいです。
Posted by さどやまかなめ at 2011年02月20日 09:13
認知システムの中への意味ネットワークを形成しなくても、資格や手続きを取れば、教師や塾講師などの教える立場に立てる事が、ごまかしの始まりなのかもしれません。
だれでも、セミナー開ける時代ですからね〜、学習者側の知恵が必要です。
また、学校でさえノルマの宿題を与えて、ごまかし勉強になりつつあるのだから、そこを補う場も必要ではないか?というのが、私の学習塾設立の動機でもあります。
まずは、指導者のごまかし勉強からのリハビリを検討しては?
私もぜひリハビリしたいです。
だれでも、セミナー開ける時代ですからね〜、学習者側の知恵が必要です。
また、学校でさえノルマの宿題を与えて、ごまかし勉強になりつつあるのだから、そこを補う場も必要ではないか?というのが、私の学習塾設立の動機でもあります。
まずは、指導者のごまかし勉強からのリハビリを検討しては?
私もぜひリハビリしたいです。
Posted by さどやまかなめ at 2011年02月20日 09:13