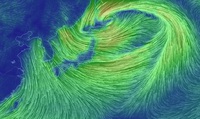2010年07月09日
沖縄と沖縄人
こんばんは!
サキシマスオウやソテツ、テリハボクの種を拾っては遊んでいる中村こと、
中村もときです。
またもや久しぶりの更新です。
最近はもっぱら森に出て色々と植物を見て回っています。
南部をウロウロ、中部をウロウロ、北部をウロウロ…。
高速の無料化は制度上浮き上がってくる問題うんぬんを抜きにして、個人的に少し嬉しいではあります。笑
最近、また考えることがあります。
この間、実家の近くにある末吉公園に行ってきました。
末吉公園は那覇にあって、大きな広場や遊具があり、子どもたちが遊んだり、
年配の方たちが集まってお喋りをしたり、カップルがいちゃいちゃしていたり、
近隣住民たち(私も含め)の憩いの場となっています。
また、末吉公園は中南部では珍しく、比較的大規模な森林が残っていて、
森の方には末吉宮という文化財も残っています。
そして、末吉公園内には様々な植物が生息します。
安謝川周辺には大きなアカギやホソバムクイヌビワ、ハマイヌビワなどがいたり、
末吉宮周辺には根の張り方がとてもすごいガジュマル、今ちょうど花を咲かせているオキナワセンニンソウなど…
場所によってはツマベニチョウという蝶の生息場所となるギョボクがあったり…
自然を観察する場所として、とても面白い場所だなぁと
最近改めて感じました。
沖縄島中南部でよく見られる典型的な植物がたくさん生えています。
そんな末吉公園をトコトコ歩いていて気になるのが、明らかに人が植えたであろう外来種。
カエンボク(アフリカンチェリー)やククイノキなどを筆頭に結構生えています。
カエンボク(この画像は末吉公園のカエンボクではないです)
幹が白くて15mぐらいの巨木になります☆

カエンボクの花です。
真っ赤に燃える炎のような花を咲かせるので「カエンボク」と呼ばれるようになったようです。

ククイノキです。(これも末吉公園の画像ではないです)
これもカエンボク同様かなりの巨木になります。
実がくるみのような実をつけます。殻を割って中身を食べることもできます。
マカダミアンナッツのような味がしますが、結構脂っぽいので食べ過ぎるとお腹を壊すかも…。
見かけはきれいですが、明らかにこの木たちだけ異質な感じで存在します。
こんな外来種が末吉公園では多々見られます。
外来種や園芸種は花がきれいだったり、見かけが美しかったりするのですが、
生態系の保存としてみると、外来種の混入は良くありません。
在来種の場合、周りの種同士で均衡を保つために、ある種がいきなり増えすぎたり、
環境を変えすぎてしまうことはありません。
しかし、外来種が入ってしまうと、その外来種と拮抗できる種がなかなか存在しないため、
競争に外来種が勝ってしまいます。そうすると、どんどん外来種が増えてしまい、
最終的には外来種が入った場所は、入る前の環境と変わってしまい生態系に大きなダメージを与えてしまうことになります。
別に園芸種を否定するわけではありませんが、園芸種は大抵外来種だったりします。
公園は公共のものではあるのですが、もともとの自然を壊してまで見かけがきれいな植物を植える必要はあるのでしょうか。
自分の家の庭でやるならまだしも、沖縄の多様な自然が残っている場所にそーいうことをしなくても…
人間が環境に与える影響って思っている以上に大きいのに…
と思いながら、末吉公園を練り歩いていくと
今度はビオトープに到着しました。
ビオトープとは生物の生息地という意味で、様々な生き物が生息できる空間のことを言います。
末吉公園ではそいうった場所を何箇所か設置しています。
そのうちのひとつのビオトープである泥でつくった池に行ってきました。
そしたらびっくり!
ビオトープの周りの草が全部刈られているではありませんか!!
たしかに、草が刈られていた方がすっきりしていて、池も見えるし、見栄えもいいのですが…
それは人間の都合であって、そこに住む虫や両性類などにとってはたまったもんじゃないです。
家の屋根や壁を全てはがされたようなものです。。。
刈った人は善意でやったかもしれませんが…これはちょっと悲しい。
人間は何かと自然を管理したがりますが、それは人間にとって都合の良い自然を作り上げるときであって、
天然の自然はほっといても遷移が始まり、いつの間にか生き物たちが集まってきてそこからどんどん豊かな生態系を作り上げていきます。
一見、草ボーボーで何か見栄えが良くないような場所でも、それは生き物たちにとっては格好の生息場所になりうるのです。人間にとっては邪魔くさくてみっともないような場所に見えるかもしれませんが…。
私が、最近また考えるようになったこと。
それは人間と自然の付き合い方です。
特に沖縄人と沖縄の自然の付き合い方。
前にも少し似たようなことを書きましたが、沖縄の人は沖縄のことに関心がなさすぎる。
それは沖縄で生まれ育ち、ずっと沖縄にいるがゆえの仕方がないことなのかもしれませんが、
沖縄のことについて知らなさすぎることが多い気がします。
別に植物や生物学を勉強しろといっているわけではなく、もっと身近な自然や文化、沖縄をつくってきたものに目を向ける必要があるんじゃないかなと思います。
沖縄のものを知らないから、異質なものが入ってきても何も感じない。むしろ、自分の都合の良いものにつくりかえていこうとしてしまうのではないでしょうか。
何だか、沖縄はいろんなところから入っていく情報におどらされて、足元を見失っている気がします。
環境や自然に関して言えば、沖縄の人は全然知らない(私も昔はそうでした)。
むしろ、沖縄人より本土から来た方の方が沖縄をよく知っていたりする。
これは、環境教育や沖縄の自然観察会、沖縄の文化を語ってくれるような講師を行っている方たちは本土の方々が多いことが物語っていると思います。
なんで、自分の住んでいるところのことを知ろうとしないのだろうか。
知る機会が減ったということは確実にあると思う。
学校でも地域のことについて勉強する時間はあまりない。
だからといって本当にこれでいいのだろうか。
沖縄を知らないまま、私たちは沖縄の自然を守っていけるのだろうか。
持続的な社会の発展を望めるのだろうか。
今も沖縄のどこかで新しい命が生まれている。
新しい命、今後沖縄で育ち、沖縄をひっぱっていく子どもたち。
私たちはその子どもたちに、何を残し・何を伝えていくべきなのであろうか。
少し立ち止まって、もう一度考えてみようと思う。
Posted by Cinnamomum_mk at 19:42│Comments(0)
│環境教育