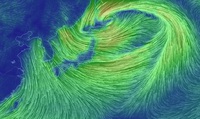2011年07月26日
カタツムリしらべ
こんにちは!
今日は少し雲がかかって涼しい1日ですね。
先日行われた「キッズマンデープロジェクト」の2回目
【カタツムリしらべ】についてリポートしていきます。
場所は毎度おなじみの那覇市にある末吉公園
今回は約20人ぐらいの方が参加してくれました♪
プログラム前半はまず、カタツムリのことについて知ろう!
皆さん知ってますか?
カタツムリと一口に言っても、色んな種類がいることを…
末吉公園には大体10種類ぐらいのカタツムリを見ることができます♪
まずは子供たちにそれを見分けられるようになってもらいましょう!
…ということで、カタツムリ同定大会です!
森の家みんみんの職員、藤井先生がカタツムリの見分け方をレクチャーしたら

いざ、カタツムリを見分けることに挑戦!

みんな必死になってこれは何、あれは何と調べていきます。
あ、このカタツムリのカラは事前にスタッフで用意したものです。
末吉公園でよくみられるカタツムリは…
・ウスカワマイマイ
・パンダナマイマイ
・シュリマイマイ
・オキナワヤマタニシ
・オキナワヤマキサゴ
・アフリカマイマイ
この6種が良く見れます。
そのほかにも、ややレアな種として
・アオミオカタニシ
・オキナワヤマタカマイマイ
の2種がいます。
さらにさらに、この末吉公園では激レアな種として
・シュリケマイマイ
・オオカサマイマイ
の2種がいます。
子供たちに同定してもらったのは、主によくみられる6種です。
その中でもいくつか特徴とともに紹介しますね。
●ウスカワマイマイ

殻の外観が丸っこいです。殻が薄くて、生きているときには殻が透明なため
カタツムリの体の模様が透けて見えています。
よく雨の日に家の壁にくっついているやつは大体こいつです。
●パンダナマイマイ

殻の側面が少し角ばっているのが分かるでしょうか?
典型的なものは、殻を横からみると殻が上から押しつぶされているような感じになっています。
ちょっと分かりにくい表現で申し訳ないです。。。
パンダナというのはアダンの学名からきています。
このマイマイが見つかった時、近くにアダンが自生していたか、南西諸島を象徴するためにつけられたのではないかと
言われています。
●シュリマイマイ

少しウスカワマイマイと雰囲気が似ていますが、ウスカワマイマイほど丸っこい形状はしていません。
比較的大きくなります。
名前がシュリとなっていますが、首里だけにいるわけではなく、首里で最初に発見されたので
それにちなんだ名前がつけられただけです。
●オキナワヤマタニシ

タニシの特徴としては出入口がマイマイに比べて、綺麗な円を描いています。
これは、タニシがフタをもつからです。マイマイと名前がついているものは
殻に体をひっこめて、出入口のところに薄い膜を張りますが、
タニシの類は膜の代わりにフタを持っていて、体をひっこめた後、そのフタで出入口を閉じます。
末吉で同定する場合は出入口が丸っこくて、触った感じがゴツゴツしていて、
殻に模様がたくさんついているという程度で同定できると思います。
他にも種によって色んな特徴があります。
普段気にしないカタツムリをじっくり観察してみると、色んな特徴が分かって面白いかもしれません♪
カタツムリというと、角の上に目がついているイメージがありますが、
その特徴は「マイマイ」のタイプです。
「タニシ」は角の下に目がついています♪
お時間ある方は今度探してみて下さい♪
さて、同定ができるようになったら、今度は今回の調査内容をレクチャーです。
今回調べるのは「アフリカマイマイ」
調査区を決めてアフリカマイマイの死んでいるやつと、生きているやつの殻の大きさを
ノギスを使って測っていく、という調査をしていきます。
ノギスの使い方を練習したら、いざ森の中へ出陣!
…の前に、事前注意。
アフリカマイマイやカタツムリの類にはよく「毒がある」という噂がありますが、
実際に毒はもっていません。がしかし、
広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう)という寄生虫をもっています。
こいつは野生の哺乳類(ネズミとか)は結構もっている寄生虫です。
この寄生虫が体内に入って、脳にまで侵入したりすると、脳機能障害を起こしてしまい、
障害が出たり、最悪の場合死に至ることもあります。
沖縄でも1件だけですが死亡例もあります。
ですが、しっかり知識をもっていれば、そんなに怖いものでもありません。
大人の皆さんは小さい頃にカタツムリを触った経験があるはず。
現にこうして生きているのは、ある程度侵入して大きな問題を起こす可能性は低いという証拠です。
カントンジュウケツセンチュウはあまり長く生きることもできないし、
胃に入った場合、胃酸でやられてしまいます。
また、皮膚から入ってくることもないです。口とか粘膜があるような場所から侵入してきます。
普段私たちは服を着ているので、ほとんどが口からの侵入になるでしょう。
ようは、カタツムリを触った後、その手のままで口を触ったりしなければ良いということです。
なので、カタツムリを触った後は手を洗うことを忘れずにやれば、
センチュウの侵入は回避できます。
今回の調査では念のためビニール手袋をして調査しました。
事前注意が終わったら、いざ出陣!
調査区に行く途中では、色んなカタツムリを観察して
「こんなところにオキナワヤマタニシがいっぱいいる!」
「ウスカワマイマイ!ウスカワマイマイ!」
名前が分かると子供たちはいつもより、じっくり観察するようになります。
進むたびカタツムリがいるので、全然前に進みません。笑
そんなこんなで調査区に到着!
調査は森の中班と森の外班に分かれて
アフリカマイマイの死んでいる殻といきているものを集めて殻の大きさを測っていきます。
約1時間程度調査をしたら、教室に戻ってデータを集計です。
死んだもの、生きているものそれぞれで
どのくらいの大きさものが、どれくらいの数いたかを棒グラフで表していきます。
すると面白い結果がでました…。
どんな結果になったかは、ぜひ次回の「キッズマンデープロジェクト」に参加した際にスタッフに聞いてみて下さい♪
次回の「キッズマンデープロジェクト」は
【落ち葉の下の生き物しらべ】です。
場所は末吉公園(那覇市首里末吉町)
時間は13:30~17:00
詳しい内容・お問い合わせは
こちらのブログをご覧ください。
http://okinawaneeprogram.ti-da.net/e3617648.html
ではでは、次回もこうご期待♪
今日は少し雲がかかって涼しい1日ですね。
先日行われた「キッズマンデープロジェクト」の2回目
【カタツムリしらべ】についてリポートしていきます。
場所は毎度おなじみの那覇市にある末吉公園
今回は約20人ぐらいの方が参加してくれました♪
プログラム前半はまず、カタツムリのことについて知ろう!
皆さん知ってますか?
カタツムリと一口に言っても、色んな種類がいることを…
末吉公園には大体10種類ぐらいのカタツムリを見ることができます♪
まずは子供たちにそれを見分けられるようになってもらいましょう!
…ということで、カタツムリ同定大会です!
森の家みんみんの職員、藤井先生がカタツムリの見分け方をレクチャーしたら

いざ、カタツムリを見分けることに挑戦!

みんな必死になってこれは何、あれは何と調べていきます。
あ、このカタツムリのカラは事前にスタッフで用意したものです。
末吉公園でよくみられるカタツムリは…
・ウスカワマイマイ
・パンダナマイマイ
・シュリマイマイ
・オキナワヤマタニシ
・オキナワヤマキサゴ
・アフリカマイマイ
この6種が良く見れます。
そのほかにも、ややレアな種として
・アオミオカタニシ
・オキナワヤマタカマイマイ
の2種がいます。
さらにさらに、この末吉公園では激レアな種として
・シュリケマイマイ
・オオカサマイマイ
の2種がいます。
子供たちに同定してもらったのは、主によくみられる6種です。
その中でもいくつか特徴とともに紹介しますね。
●ウスカワマイマイ

殻の外観が丸っこいです。殻が薄くて、生きているときには殻が透明なため
カタツムリの体の模様が透けて見えています。
よく雨の日に家の壁にくっついているやつは大体こいつです。
●パンダナマイマイ

殻の側面が少し角ばっているのが分かるでしょうか?
典型的なものは、殻を横からみると殻が上から押しつぶされているような感じになっています。
ちょっと分かりにくい表現で申し訳ないです。。。
パンダナというのはアダンの学名からきています。
このマイマイが見つかった時、近くにアダンが自生していたか、南西諸島を象徴するためにつけられたのではないかと
言われています。
●シュリマイマイ

少しウスカワマイマイと雰囲気が似ていますが、ウスカワマイマイほど丸っこい形状はしていません。
比較的大きくなります。
名前がシュリとなっていますが、首里だけにいるわけではなく、首里で最初に発見されたので
それにちなんだ名前がつけられただけです。
●オキナワヤマタニシ

タニシの特徴としては出入口がマイマイに比べて、綺麗な円を描いています。
これは、タニシがフタをもつからです。マイマイと名前がついているものは
殻に体をひっこめて、出入口のところに薄い膜を張りますが、
タニシの類は膜の代わりにフタを持っていて、体をひっこめた後、そのフタで出入口を閉じます。
末吉で同定する場合は出入口が丸っこくて、触った感じがゴツゴツしていて、
殻に模様がたくさんついているという程度で同定できると思います。
他にも種によって色んな特徴があります。
普段気にしないカタツムリをじっくり観察してみると、色んな特徴が分かって面白いかもしれません♪
カタツムリというと、角の上に目がついているイメージがありますが、
その特徴は「マイマイ」のタイプです。
「タニシ」は角の下に目がついています♪
お時間ある方は今度探してみて下さい♪
さて、同定ができるようになったら、今度は今回の調査内容をレクチャーです。
今回調べるのは「アフリカマイマイ」
調査区を決めてアフリカマイマイの死んでいるやつと、生きているやつの殻の大きさを
ノギスを使って測っていく、という調査をしていきます。
ノギスの使い方を練習したら、いざ森の中へ出陣!
…の前に、事前注意。
アフリカマイマイやカタツムリの類にはよく「毒がある」という噂がありますが、
実際に毒はもっていません。がしかし、
広東住血線虫(かんとんじゅうけつせんちゅう)という寄生虫をもっています。
こいつは野生の哺乳類(ネズミとか)は結構もっている寄生虫です。
この寄生虫が体内に入って、脳にまで侵入したりすると、脳機能障害を起こしてしまい、
障害が出たり、最悪の場合死に至ることもあります。
沖縄でも1件だけですが死亡例もあります。
ですが、しっかり知識をもっていれば、そんなに怖いものでもありません。
大人の皆さんは小さい頃にカタツムリを触った経験があるはず。
現にこうして生きているのは、ある程度侵入して大きな問題を起こす可能性は低いという証拠です。
カントンジュウケツセンチュウはあまり長く生きることもできないし、
胃に入った場合、胃酸でやられてしまいます。
また、皮膚から入ってくることもないです。口とか粘膜があるような場所から侵入してきます。
普段私たちは服を着ているので、ほとんどが口からの侵入になるでしょう。
ようは、カタツムリを触った後、その手のままで口を触ったりしなければ良いということです。
なので、カタツムリを触った後は手を洗うことを忘れずにやれば、
センチュウの侵入は回避できます。
今回の調査では念のためビニール手袋をして調査しました。
事前注意が終わったら、いざ出陣!
調査区に行く途中では、色んなカタツムリを観察して
「こんなところにオキナワヤマタニシがいっぱいいる!」
「ウスカワマイマイ!ウスカワマイマイ!」
名前が分かると子供たちはいつもより、じっくり観察するようになります。
進むたびカタツムリがいるので、全然前に進みません。笑
そんなこんなで調査区に到着!
調査は森の中班と森の外班に分かれて
アフリカマイマイの死んでいる殻といきているものを集めて殻の大きさを測っていきます。
約1時間程度調査をしたら、教室に戻ってデータを集計です。
死んだもの、生きているものそれぞれで
どのくらいの大きさものが、どれくらいの数いたかを棒グラフで表していきます。
すると面白い結果がでました…。
どんな結果になったかは、ぜひ次回の「キッズマンデープロジェクト」に参加した際にスタッフに聞いてみて下さい♪
次回の「キッズマンデープロジェクト」は
【落ち葉の下の生き物しらべ】です。
場所は末吉公園(那覇市首里末吉町)
時間は13:30~17:00
詳しい内容・お問い合わせは
こちらのブログをご覧ください。
http://okinawaneeprogram.ti-da.net/e3617648.html
ではでは、次回もこうご期待♪
Posted by Cinnamomum_mk at 13:56│Comments(0)
│植物