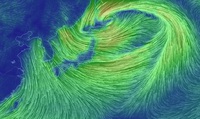2011年08月09日
公園のアリしらべ
こんばんは(^O^)
今回の台風は長く居座って大変でしたね。
私の家の窓ガラスが一か所割れてビックリしました。
皆さんは大丈夫だったでしょうか?
さて、今日8月8日(月)に行われた
「キッズマンデープロジェクト」第4回目
「公園のアリしらべ」をリポートしていきます。
普段の生活の中で何気ないところに出現するアリ。
身近な生き物ほど気を付けて見ないもので、
アリを見つけても中々まじまじと観察することは少なかったりするのではないでしょうか(^O^)
そんなアリを今日はテーマにして観察会をしていきました♪
アリの体は大きく四つに分けられます。
・頭部(とうぶ)
・胸部(きょうぶ)
・腹柄(ふくへい)
・腹部(ふくぶ)
図に表すとこんな感じ。(アシナガキアリ)

テキトーに書いたので、下手な部分はご了承ください。笑
ちなみに本物はこんな感じです。
アシナガキアリ

アリを見分けるポイントの一つとして
胸部と腹部を間にある「腹柄」を見ます。
上の図は腹柄がひとつのタイプです。
この腹柄が2つあるタイプ(フタフシアリと呼ばれる仲間)もいます。
まずは大雑把にこの2タイプで分けていきます。
末吉公園でよくみられるアリとしては
『腹柄が1つのタイプ』
・ハリアリの仲間(針をもち、腹部がくびれ、腹柄が高い)
・ヤマアリの仲間(腹部の先端は丸くすぼまって毛が生える)
・カタアリの仲間(腹部先端はスリットで毛はない)
『腹柄が2つのタイプ』
・フタフシアリの仲間(腹柄が2つある)
こんな感じです。
今回のキッズマンデーでは
日本産アリ画像データベースにある画像をもとに、
種レベルまで同定できる個体は同定して、
そこまでは難しい個体は、おおよそ何の仲間かというところまでは同定しました。
これが日本産アリ画像データベースです。
「日本産アリ画像データベース」
http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/J/index.html
日本各地のアリの画像が載っているサイトで、
信頼性も高いので、アリの画像を使うときはこちらはオススメです。
さてさて、アリの説明はこんな感じにしておき
キッズマンデーの内容を紹介していきます。
4回目も大勢の親子が参加してくれました(^O^)

いつも30名前後は集まってくれています。
いつも通り、キッズマンデープロジェクトと今日の流れについて
簡単に説明したあとは…
実際にアリを捕まえて観察しました♪
でも、小さな昆虫などを素手で捕まえようとすると
どうしても潰してしまったり、傷つけてしまうことがあります。
そこで活躍するのが「吸虫管」
教材屋さんで売っていたりするのですが、結構手軽に作れるものなので、
今回はみんなで吸虫管を手作りしました。
作り方は

まず、径の大きさが違う大中小チューブを3種類、ストロー、お茶フィルターを用意します。
大チューブは中チューブにジョイントできる大きさ
中チューブは小チューブにジョイントできる大きさです。(チューブ径の大きさ調べてなくてすいません)
ストローの径は中チューブにジョイントできるぐらいの大きさです。
これを図のように切って全部ジョイントすると

こんな感じの吸虫管ができます。
チューブのところを口に、ストローの部分を狙い定めた虫へ
向けて一気に吸い込みます。
すると、大チューブの中に虫が入ります。
(口に虫が入らないように、口側のチューブにはお茶フィルターを挟みます)
それを双眼実体顕微鏡(ファーブル)で観察します。
チューブの中にいるままだと、観察しにくいという場合は
お皿にアルコールを少し垂らして、その上にアリを置いて
アリを酔っぱらわせます。(アルコール濃度が濃いとアリは死んじゃいます。
大体で薄めたので正確な濃度は分かりませんが、20%ぐらいがちょうどイイ感じです。)

動きを止めたアリを観察している様子です。

保護者の方と一緒に、このアリは何アリなのか同定していきます。
結構難しいので、スタッフの人たちと一緒に観察していきます。
でも、これはまだ練習。
今度は、何種類かトラップをしかけて、そこにどんなアリが集まるか観察していきます。

トラップのエサにするのはこの3種類。
・ツナ
・ピーナツバター
・いちごジャム
タンパク質系、ナッツ系(木の実)、糖質系の3タイプにしました。
(ピーナツバターも糖質系では!?という質問は受けません。笑)
この3種類のエサを「森の外」・「森の中」に仕掛けます。
・・・30分後・・・
仕掛けたトラップを回収して
またもや顕微鏡を使ってひたすら観察です。

エサや場所、トラップを回収する時間の違いで集まってくる種も変わってきます。
今回は時間の関係もあり、場所やエサの違いによる種の違いについて
詳しいまとめはできませんでしたが、
夏休みの自由研究で、家の周りにいるアリを使ってデータをとってみたら
面白い結果になるかもしれません。
私が小学生だったらやりたかった題材だなぁと思う今日この頃。
なんか、まとまりないリポートで申し訳ないです。
ともかく、自然をいっぱい学んで遊んでいます。
次回は今年のキッズマンデー最終回
「森のイチジクしらべ」です。
森の植物(とくにイチジクの仲間)を探し回って、どんな環境にどんな植物がいるのかを
学んでいく会です。
ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
詳しい内容・お問い合わせは
「おきなわイーイープログラムづくりプロジェクト」
http://okinawaneeprogram.ti-da.net/e3617648.html
こちらをご覧ください。
それでは失礼します。
今回の台風は長く居座って大変でしたね。
私の家の窓ガラスが一か所割れてビックリしました。
皆さんは大丈夫だったでしょうか?
さて、今日8月8日(月)に行われた
「キッズマンデープロジェクト」第4回目
「公園のアリしらべ」をリポートしていきます。
普段の生活の中で何気ないところに出現するアリ。
身近な生き物ほど気を付けて見ないもので、
アリを見つけても中々まじまじと観察することは少なかったりするのではないでしょうか(^O^)
そんなアリを今日はテーマにして観察会をしていきました♪
アリの体は大きく四つに分けられます。
・頭部(とうぶ)
・胸部(きょうぶ)
・腹柄(ふくへい)
・腹部(ふくぶ)
図に表すとこんな感じ。(アシナガキアリ)

テキトーに書いたので、下手な部分はご了承ください。笑
ちなみに本物はこんな感じです。
アシナガキアリ

アリを見分けるポイントの一つとして
胸部と腹部を間にある「腹柄」を見ます。
上の図は腹柄がひとつのタイプです。
この腹柄が2つあるタイプ(フタフシアリと呼ばれる仲間)もいます。
まずは大雑把にこの2タイプで分けていきます。
末吉公園でよくみられるアリとしては
『腹柄が1つのタイプ』
・ハリアリの仲間(針をもち、腹部がくびれ、腹柄が高い)
・ヤマアリの仲間(腹部の先端は丸くすぼまって毛が生える)
・カタアリの仲間(腹部先端はスリットで毛はない)
『腹柄が2つのタイプ』
・フタフシアリの仲間(腹柄が2つある)
こんな感じです。
今回のキッズマンデーでは
日本産アリ画像データベースにある画像をもとに、
種レベルまで同定できる個体は同定して、
そこまでは難しい個体は、おおよそ何の仲間かというところまでは同定しました。
これが日本産アリ画像データベースです。
「日本産アリ画像データベース」
http://ant.edb.miyakyo-u.ac.jp/J/index.html
日本各地のアリの画像が載っているサイトで、
信頼性も高いので、アリの画像を使うときはこちらはオススメです。
さてさて、アリの説明はこんな感じにしておき
キッズマンデーの内容を紹介していきます。
4回目も大勢の親子が参加してくれました(^O^)

いつも30名前後は集まってくれています。
いつも通り、キッズマンデープロジェクトと今日の流れについて
簡単に説明したあとは…
実際にアリを捕まえて観察しました♪
でも、小さな昆虫などを素手で捕まえようとすると
どうしても潰してしまったり、傷つけてしまうことがあります。
そこで活躍するのが「吸虫管」
教材屋さんで売っていたりするのですが、結構手軽に作れるものなので、
今回はみんなで吸虫管を手作りしました。
作り方は

まず、径の大きさが違う大中小チューブを3種類、ストロー、お茶フィルターを用意します。
大チューブは中チューブにジョイントできる大きさ
中チューブは小チューブにジョイントできる大きさです。(チューブ径の大きさ調べてなくてすいません)
ストローの径は中チューブにジョイントできるぐらいの大きさです。
これを図のように切って全部ジョイントすると

こんな感じの吸虫管ができます。
チューブのところを口に、ストローの部分を狙い定めた虫へ
向けて一気に吸い込みます。
すると、大チューブの中に虫が入ります。
(口に虫が入らないように、口側のチューブにはお茶フィルターを挟みます)
それを双眼実体顕微鏡(ファーブル)で観察します。
チューブの中にいるままだと、観察しにくいという場合は
お皿にアルコールを少し垂らして、その上にアリを置いて
アリを酔っぱらわせます。(アルコール濃度が濃いとアリは死んじゃいます。
大体で薄めたので正確な濃度は分かりませんが、20%ぐらいがちょうどイイ感じです。)

動きを止めたアリを観察している様子です。

保護者の方と一緒に、このアリは何アリなのか同定していきます。
結構難しいので、スタッフの人たちと一緒に観察していきます。
でも、これはまだ練習。
今度は、何種類かトラップをしかけて、そこにどんなアリが集まるか観察していきます。

トラップのエサにするのはこの3種類。
・ツナ
・ピーナツバター
・いちごジャム
タンパク質系、ナッツ系(木の実)、糖質系の3タイプにしました。
(ピーナツバターも糖質系では!?という質問は受けません。笑)
この3種類のエサを「森の外」・「森の中」に仕掛けます。
・・・30分後・・・
仕掛けたトラップを回収して
またもや顕微鏡を使ってひたすら観察です。

エサや場所、トラップを回収する時間の違いで集まってくる種も変わってきます。
今回は時間の関係もあり、場所やエサの違いによる種の違いについて
詳しいまとめはできませんでしたが、
夏休みの自由研究で、家の周りにいるアリを使ってデータをとってみたら
面白い結果になるかもしれません。
私が小学生だったらやりたかった題材だなぁと思う今日この頃。
なんか、まとまりないリポートで申し訳ないです。
ともかく、自然をいっぱい学んで遊んでいます。
次回は今年のキッズマンデー最終回
「森のイチジクしらべ」です。
森の植物(とくにイチジクの仲間)を探し回って、どんな環境にどんな植物がいるのかを
学んでいく会です。
ぜひ参加してみてはいかがでしょうか。
詳しい内容・お問い合わせは
「おきなわイーイープログラムづくりプロジェクト」
http://okinawaneeprogram.ti-da.net/e3617648.html
こちらをご覧ください。
それでは失礼します。
Posted by Cinnamomum_mk at 17:41│Comments(0)
│植物