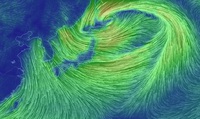2011年08月19日
森のイチジクしらべ
こんにちは。
ここんところずっと
インターネットの調子が悪くて、なかなか更新できずにいました。
先日、那覇市立森の家みんみんで行われた
「キッズマンデープロジェクト」
第5回「森のイチジクしらべ」の様子をリポートしていきます。
今年のキッズマンデーはこれが最後です。
今日のテーマはイチジク。
本土ではよく食べられたりしているのですが、
沖縄の人はあまり食べる習慣がないのか、店頭に置いてあることも少ないですし、
実際に食べたことある人も少ないと思います。
食用になるイチジクの仲間は沖縄に結構たくさんいます。
この末吉公園には10種のイチジクの仲間(イチジク属)が生育しています。
・ホソバムクイヌビワ
・シダレガジュマル(シロガジュマル)
・インドゴムノキ
・イヌビワ
・ガジュマル
・オオイタビ
・フィッカスハワイ
・オオバイヌビワ
・アコウ
・ハマイヌビワ
この中でも今回は、在来種の7種(シダレガジュマル、インドゴムノキ、フィッカスハワイ以外)を取り上げて
キッズマンデーを進めていきました。
まずは、これらの種が同定できるようになるために、
葉っぱを見て触って、どれがどの種というのを覚えていきます。

用意された葉っぱには触った感じが「ツルツル」しているものと「ザラザラ」しているものがあります。
それを触って、まずはツルツル葉っぱとザラザラ葉っぱに分けていきます。
それから、葉っぱそれぞれの特徴(色、形、質感、触感など)を捉えながら
同定の練習をしていきます。

子供たちはお気に入りの葉っぱを見つけたら、もうそれしか見てくれません。笑
私の担当したグループでは葉っぱの大きい「オオバイヌビワ」が特に人気でした。
大体、葉っぱの特徴が分かってきたら、今度は森に出て調査を開始です。
コースを決めて、コース沿いのどこにイヌビワ属が分布しているか地図上に落としていきます。

壁にオオイタビが生えてる!
というスタッフの声に皆集まって、ジロジロ観察です。
ちなみにオオイタビはこんな感じです。

つる性の植物ですが、ブドウのようにヒゲを出してグルグル巻きつくのではなく、
不定根と呼ばれる根っこを茎から出して、その根っこで壁にへばりついているタイプです。
実は赤ちゃんの握りこぶしぐらいの大きさになり、熟すると食べれはしますが、
そんなに美味しいものでもありません。笑
沖縄では石垣にくっついていることが多いです。
きっと、こいつを這わせて石垣を補強するのと同時に
白い琉球石灰岩が太陽の光を照り返すのを防いでいるのでしょう。
この流れでイチジク属をいくつか紹介していきたいと思います。

ガジュマルです。これは沖縄でもっともポピュラーな植物と言ってもいいのではないでしょうか。
昔、ガジュマルの大木にはキジムナーが住んでいるんだよと教えられたものです。笑
この植物は、岩の上を好みます。というか、自然状態で土の上から芽生えることはほとんどありません。
ガジュマルがすくすくと育っているのは、ほかの植物があんまり生えていない岩の上だったり、
ある程度大きくなった植物の幹のくぼみなどです。
なぜ、土の上(自然状態。植栽を除く)でほとんど芽生えがないのか詳しいことはまだわかっていないのですが、
周りの植物が出している何らかの物質によって発芽が抑制されているのではないかと思われます。
写真のようにヒゲ(気根)を出して、岩上で不安定な自分の体を支えようとします。
また、このヒゲをほかの植物に絡めて絞め殺したりもします。
個人的には、分かってないことも含めてかなり面白い生態をもっていて、魅力的な植物だなと思っています。

これはイヌビワです。
名前の由来はビワのような実をつけるけど、ビワより劣る(いぬ≒いらない)植物なので、
イヌビワと名前がついているようです。
その他、イヌと名前がつく植物はいくつかあり、イヌという意味はすべて「~より劣る、いらない」といった意味合いで
使われています。動物の犬とは関係ありません。
沖縄の有用木材の一つ、イヌマキ(チャーギ)もマキという植物には劣るという意味でつけられた名前です。
本土ではマキという植物が有用木材で、イヌマキはさほど必要とされていません。
でも、沖縄ぐらい南にくると、家屋にシロアリが大量に発生するので、シロアリに耐性をもつイヌマキは重宝されたのです。
本土ではイヌマキですが、沖縄ではイルマキですね。笑
おっと、余談が多くなりました。
イヌビワの実も熟すると食べられます。まぁ、これもあんまり美味しいものではありませんが…。
比較的林縁部などの光がよく当たる場所に好んで分布します。
このようにイヌビワ属といっても、それぞれいろんな特徴があって分布する場所も異なってきます。
それを地図上に落としていくと、植物分布と環境の関係性が何となく見えてくるというわけです。

調査を終えたら、教室にてデータを集計していきます。
データをここで公開することはできませんが、予想通り植物と環境との相関を少し見ることができました。
ガジュマルが分布しているところは岩がゴロゴロしている場所。
イヌビワが分布している場所は明るい場所。
ホソバムクイヌビワが分布している場所は水辺。
などなど、植物がその特徴を生かして、住み分けていることが分かります。
普段、何となく森や緑地を見ているだけでは、ただ単なる「緑」としか認識されませんが、
こうやって植物の名前やその特徴などを知ることで、その場所がどんな環境か分かり、森の営みを感じることができるようになってきます。きっと、昔の人はこういったことを経験的に感じ取り、その地域・環境にある植物をつかった文化・風習をつくりだしていったのでしょう。
しかし、近年はこういった環境と植物との関係性を考慮しないで、植樹などの緑化が行なわれていることが少なくありません。
さらには、花が派手でキレイという理由で外来種がバンバン植えられているのが現状です。
これは、私たち先祖が培ってきた土地それぞれの文化を、知らぬ間に消し去ってしまっていることにつながるのではないでしょうか。
植物と環境の関係性を知ることは、生物学的な知識を増やすことに加えて、
文化・伝統の継承にもつながっていくのだと私は思います。
そういった意味でも、沖縄在来の自然というものは大事にしていきたいし、伝えていきたいなぁと思います。
また脱線してしまいました。乱文で申し訳ないです。
今回のまとめはこれということで。笑
今年のキッズマンデーは終了です。
ご参加いただいた方、ありがとうございました。
森の家みんみんでは定期的に自然観察学習会を開催しております。
以下のブログで紹介しています。
http://okinawaneeprogram.ti-da.net/
※追記
イチジクしらべなのにイチジクについては全然書いてませんでした。笑
少しイチジクについて解説を。
イチジクは漢字で書くと「無花果」と書きます。
ガジュマルとか年がら年中実をつけているのに、花は見たことがないなぁと思ったことはありませんか?
漢字でかくように、一見花が無いように見えるのがイチジクの特徴です。
でも、私たちからは見えてないだけで、ちゃんと花は咲いています。
その答えは私たちが実だと思っていたものの中に隠れています。
ちょっとイヌビワを用いてイチジクがどんな構造をしているのか見ていきましょう。

これが実。

これが葉っぱ。
でも、今回使うのは実だけです。

まずは実をカッターで半分に切ります。
カッターの刃はやっぱり、プロ仕様のオルファに限ります。
切れ味抜群!
半分にしてみるとこんな感じです。(ピンボケ万歳!)

中に何かモシャモシャしたものがあります。

じつは、これが花なんです。
双眼実体顕微鏡を使って見てみましょう。


もやしのように見えるのが花です。
一般的に花といえば

こんな感じで、花びらやおしべとめしべが外に開いて、
虫や鳥に花粉を運んでもらって受粉しているイメージですが、(↓こんな感じで)

イチジク属は違う戦略をもっています。
以下、「JT生命誌研究館」の研究紹介:昆虫と植物の共進化ラボ「生命誌32号」より引用
イチジクの最大の特徴は,いつ花が咲いたのかわからないうちに熟している「果実」にある。本当は,その部分を「果実」と呼ぶのは適当ではない。イチジクの「果実」を半分に割ると,中にたくさんの小さな粒が詰まっていて,その一つ一つが内側に細長い柄でつながっている。じつはこの粒がイチジクの花だ。つまりイチジクの「果実」とされているものは,変形した花の集まり(花か序じょ)からできたものである。イチジクの花の集まりは特別に「花のう」と呼ぶ。
花のう内に通じる唯一の口の部分は,鱗りん片ぺんで堅く閉じていて,イチジクの花粉はハナバチやチョウなどの昆虫に運ばれることはなく,風でも飛ばない。いったい何がイチジクの花粉を運ぶのだろう。授粉を受ける時期の花のうを見張っていると,体長約2 mm の,ショウジョウバエのように小さな昆虫,イチジクコバチの仲間(以下コバチと略)が現れる。このコバチが,イチジクの花粉の運び手だ。
このコバチは,雌花が咲く時にわずかに開く鱗片の隙間から花のうに入り込んで授粉するのだが,その際,ほかの送粉昆虫と同じように「報酬」を受け取る。コバチが得る「報酬」は,自分の餌ではなく幼虫の餌だ。コバチは花粉専用の「ポケット」をもち――なんと洒落た運び手!――,そこから花粉を取り出して授粉すると同時に,その花の雌しべの先から産卵管を差し込んで卵を産む。幼虫はここにできる種子を食べて育つのだ。同じ花のうの中でも,雌しべの長さに違いがあるので,コバチの産卵管よりも雌しべが短い花には卵が産みつけられるが,雌しべが長い花には産卵管が届かず,めでたく種子が実る。コバチの幼虫も育つしイチジクの種子もできるという仕組みだ。ただ,産卵後のコバチは二度と飛び出せず,花のうの中で一生を終える。産みつけられた卵がどうなるか。ここから先は図を見ていただきたい。

雌花が受粉してから,雄花が咲くまでの時間のずれは,見事にコバチ一世代分の時間になる。雄のコバチは生まれた花のうで短い生涯を閉じ,餌を採らない成虫の雌も,自由に飛び回れる時間はせいぜい半日から1日だ。強い日差しや風雨,天敵の待つ命がけの旅のはてに,産卵に適した花のうを探し当てられたものだけが,次の世代を残す。
花は自らの種子を餌に,送粉昆虫の「ゆりかご」となって成虫まで育て,育ったコバチは,イチジクの「空飛ぶ花粉」となる。花と送粉昆虫の関係にはいろいろあるが,これほど密な関係は滅多にない。イチジクはコバチのためにあり,コバチはイチジクのためにあるのではないかと錯覚してしまうほどだ。
イチジクの種類ごとに花粉を運ぶコバチの種類も決まっており,祖先種で獲得された1 対1 の共生関係を維持している。
引用終わり
このようにイチジクはイチジクコバチとの共生関係をつくるという面白い戦略をとっているのです。
私はこれを知った時は衝撃でした。
とまぁ、こんなイチジクに関しての解説(ほどんど引用ですけど)はこんな感じです。
家の近くにあるイチジク属の花をとって、コバチを探してはいかがでしょう?
ではでは。
ここんところずっと
インターネットの調子が悪くて、なかなか更新できずにいました。
先日、那覇市立森の家みんみんで行われた
「キッズマンデープロジェクト」
第5回「森のイチジクしらべ」の様子をリポートしていきます。
今年のキッズマンデーはこれが最後です。
今日のテーマはイチジク。
本土ではよく食べられたりしているのですが、
沖縄の人はあまり食べる習慣がないのか、店頭に置いてあることも少ないですし、
実際に食べたことある人も少ないと思います。
食用になるイチジクの仲間は沖縄に結構たくさんいます。
この末吉公園には10種のイチジクの仲間(イチジク属)が生育しています。
・ホソバムクイヌビワ
・シダレガジュマル(シロガジュマル)
・インドゴムノキ
・イヌビワ
・ガジュマル
・オオイタビ
・フィッカスハワイ
・オオバイヌビワ
・アコウ
・ハマイヌビワ
この中でも今回は、在来種の7種(シダレガジュマル、インドゴムノキ、フィッカスハワイ以外)を取り上げて
キッズマンデーを進めていきました。
まずは、これらの種が同定できるようになるために、
葉っぱを見て触って、どれがどの種というのを覚えていきます。

用意された葉っぱには触った感じが「ツルツル」しているものと「ザラザラ」しているものがあります。
それを触って、まずはツルツル葉っぱとザラザラ葉っぱに分けていきます。
それから、葉っぱそれぞれの特徴(色、形、質感、触感など)を捉えながら
同定の練習をしていきます。

子供たちはお気に入りの葉っぱを見つけたら、もうそれしか見てくれません。笑
私の担当したグループでは葉っぱの大きい「オオバイヌビワ」が特に人気でした。
大体、葉っぱの特徴が分かってきたら、今度は森に出て調査を開始です。
コースを決めて、コース沿いのどこにイヌビワ属が分布しているか地図上に落としていきます。

壁にオオイタビが生えてる!
というスタッフの声に皆集まって、ジロジロ観察です。
ちなみにオオイタビはこんな感じです。

つる性の植物ですが、ブドウのようにヒゲを出してグルグル巻きつくのではなく、
不定根と呼ばれる根っこを茎から出して、その根っこで壁にへばりついているタイプです。
実は赤ちゃんの握りこぶしぐらいの大きさになり、熟すると食べれはしますが、
そんなに美味しいものでもありません。笑
沖縄では石垣にくっついていることが多いです。
きっと、こいつを這わせて石垣を補強するのと同時に
白い琉球石灰岩が太陽の光を照り返すのを防いでいるのでしょう。
この流れでイチジク属をいくつか紹介していきたいと思います。

ガジュマルです。これは沖縄でもっともポピュラーな植物と言ってもいいのではないでしょうか。
昔、ガジュマルの大木にはキジムナーが住んでいるんだよと教えられたものです。笑
この植物は、岩の上を好みます。というか、自然状態で土の上から芽生えることはほとんどありません。
ガジュマルがすくすくと育っているのは、ほかの植物があんまり生えていない岩の上だったり、
ある程度大きくなった植物の幹のくぼみなどです。
なぜ、土の上(自然状態。植栽を除く)でほとんど芽生えがないのか詳しいことはまだわかっていないのですが、
周りの植物が出している何らかの物質によって発芽が抑制されているのではないかと思われます。
写真のようにヒゲ(気根)を出して、岩上で不安定な自分の体を支えようとします。
また、このヒゲをほかの植物に絡めて絞め殺したりもします。
個人的には、分かってないことも含めてかなり面白い生態をもっていて、魅力的な植物だなと思っています。

これはイヌビワです。
名前の由来はビワのような実をつけるけど、ビワより劣る(いぬ≒いらない)植物なので、
イヌビワと名前がついているようです。
その他、イヌと名前がつく植物はいくつかあり、イヌという意味はすべて「~より劣る、いらない」といった意味合いで
使われています。動物の犬とは関係ありません。
沖縄の有用木材の一つ、イヌマキ(チャーギ)もマキという植物には劣るという意味でつけられた名前です。
本土ではマキという植物が有用木材で、イヌマキはさほど必要とされていません。
でも、沖縄ぐらい南にくると、家屋にシロアリが大量に発生するので、シロアリに耐性をもつイヌマキは重宝されたのです。
本土ではイヌマキですが、沖縄ではイルマキですね。笑
おっと、余談が多くなりました。
イヌビワの実も熟すると食べられます。まぁ、これもあんまり美味しいものではありませんが…。
比較的林縁部などの光がよく当たる場所に好んで分布します。
このようにイヌビワ属といっても、それぞれいろんな特徴があって分布する場所も異なってきます。
それを地図上に落としていくと、植物分布と環境の関係性が何となく見えてくるというわけです。

調査を終えたら、教室にてデータを集計していきます。
データをここで公開することはできませんが、予想通り植物と環境との相関を少し見ることができました。
ガジュマルが分布しているところは岩がゴロゴロしている場所。
イヌビワが分布している場所は明るい場所。
ホソバムクイヌビワが分布している場所は水辺。
などなど、植物がその特徴を生かして、住み分けていることが分かります。
普段、何となく森や緑地を見ているだけでは、ただ単なる「緑」としか認識されませんが、
こうやって植物の名前やその特徴などを知ることで、その場所がどんな環境か分かり、森の営みを感じることができるようになってきます。きっと、昔の人はこういったことを経験的に感じ取り、その地域・環境にある植物をつかった文化・風習をつくりだしていったのでしょう。
しかし、近年はこういった環境と植物との関係性を考慮しないで、植樹などの緑化が行なわれていることが少なくありません。
さらには、花が派手でキレイという理由で外来種がバンバン植えられているのが現状です。
これは、私たち先祖が培ってきた土地それぞれの文化を、知らぬ間に消し去ってしまっていることにつながるのではないでしょうか。
植物と環境の関係性を知ることは、生物学的な知識を増やすことに加えて、
文化・伝統の継承にもつながっていくのだと私は思います。
そういった意味でも、沖縄在来の自然というものは大事にしていきたいし、伝えていきたいなぁと思います。
また脱線してしまいました。乱文で申し訳ないです。
今回のまとめはこれということで。笑
今年のキッズマンデーは終了です。
ご参加いただいた方、ありがとうございました。
森の家みんみんでは定期的に自然観察学習会を開催しております。
以下のブログで紹介しています。
http://okinawaneeprogram.ti-da.net/
※追記
イチジクしらべなのにイチジクについては全然書いてませんでした。笑
少しイチジクについて解説を。
イチジクは漢字で書くと「無花果」と書きます。
ガジュマルとか年がら年中実をつけているのに、花は見たことがないなぁと思ったことはありませんか?
漢字でかくように、一見花が無いように見えるのがイチジクの特徴です。
でも、私たちからは見えてないだけで、ちゃんと花は咲いています。
その答えは私たちが実だと思っていたものの中に隠れています。
ちょっとイヌビワを用いてイチジクがどんな構造をしているのか見ていきましょう。

これが実。

これが葉っぱ。
でも、今回使うのは実だけです。

まずは実をカッターで半分に切ります。
カッターの刃はやっぱり、プロ仕様のオルファに限ります。
切れ味抜群!
半分にしてみるとこんな感じです。(ピンボケ万歳!)

中に何かモシャモシャしたものがあります。

じつは、これが花なんです。
双眼実体顕微鏡を使って見てみましょう。


もやしのように見えるのが花です。
一般的に花といえば

こんな感じで、花びらやおしべとめしべが外に開いて、
虫や鳥に花粉を運んでもらって受粉しているイメージですが、(↓こんな感じで)

イチジク属は違う戦略をもっています。
以下、「JT生命誌研究館」の研究紹介:昆虫と植物の共進化ラボ「生命誌32号」より引用
イチジクの最大の特徴は,いつ花が咲いたのかわからないうちに熟している「果実」にある。本当は,その部分を「果実」と呼ぶのは適当ではない。イチジクの「果実」を半分に割ると,中にたくさんの小さな粒が詰まっていて,その一つ一つが内側に細長い柄でつながっている。じつはこの粒がイチジクの花だ。つまりイチジクの「果実」とされているものは,変形した花の集まり(花か序じょ)からできたものである。イチジクの花の集まりは特別に「花のう」と呼ぶ。
花のう内に通じる唯一の口の部分は,鱗りん片ぺんで堅く閉じていて,イチジクの花粉はハナバチやチョウなどの昆虫に運ばれることはなく,風でも飛ばない。いったい何がイチジクの花粉を運ぶのだろう。授粉を受ける時期の花のうを見張っていると,体長約2 mm の,ショウジョウバエのように小さな昆虫,イチジクコバチの仲間(以下コバチと略)が現れる。このコバチが,イチジクの花粉の運び手だ。
このコバチは,雌花が咲く時にわずかに開く鱗片の隙間から花のうに入り込んで授粉するのだが,その際,ほかの送粉昆虫と同じように「報酬」を受け取る。コバチが得る「報酬」は,自分の餌ではなく幼虫の餌だ。コバチは花粉専用の「ポケット」をもち――なんと洒落た運び手!――,そこから花粉を取り出して授粉すると同時に,その花の雌しべの先から産卵管を差し込んで卵を産む。幼虫はここにできる種子を食べて育つのだ。同じ花のうの中でも,雌しべの長さに違いがあるので,コバチの産卵管よりも雌しべが短い花には卵が産みつけられるが,雌しべが長い花には産卵管が届かず,めでたく種子が実る。コバチの幼虫も育つしイチジクの種子もできるという仕組みだ。ただ,産卵後のコバチは二度と飛び出せず,花のうの中で一生を終える。産みつけられた卵がどうなるか。ここから先は図を見ていただきたい。

雌花が受粉してから,雄花が咲くまでの時間のずれは,見事にコバチ一世代分の時間になる。雄のコバチは生まれた花のうで短い生涯を閉じ,餌を採らない成虫の雌も,自由に飛び回れる時間はせいぜい半日から1日だ。強い日差しや風雨,天敵の待つ命がけの旅のはてに,産卵に適した花のうを探し当てられたものだけが,次の世代を残す。
花は自らの種子を餌に,送粉昆虫の「ゆりかご」となって成虫まで育て,育ったコバチは,イチジクの「空飛ぶ花粉」となる。花と送粉昆虫の関係にはいろいろあるが,これほど密な関係は滅多にない。イチジクはコバチのためにあり,コバチはイチジクのためにあるのではないかと錯覚してしまうほどだ。
イチジクの種類ごとに花粉を運ぶコバチの種類も決まっており,祖先種で獲得された1 対1 の共生関係を維持している。
引用終わり
このようにイチジクはイチジクコバチとの共生関係をつくるという面白い戦略をとっているのです。
私はこれを知った時は衝撃でした。
とまぁ、こんなイチジクに関しての解説(ほどんど引用ですけど)はこんな感じです。
家の近くにあるイチジク属の花をとって、コバチを探してはいかがでしょう?
ではでは。
Posted by Cinnamomum_mk at 13:48│Comments(0)
│植物