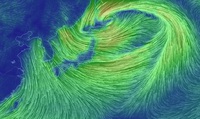2012年07月13日
思ひ出ぽろぽろ
こんばんは。
このところ毎日更新でございます。
結構、頭の整理になったり、休憩になったりして良いかも。
っとこんな忙しい時期になって思います。
こんなことやってるヒマあったら単語の一つでも覚えろと
誰かに言われないかとビクビクしている今日この頃。
どうも僕です。
んー、今日は特に珍しいことはなく。
某学校の生物部の子たちとカタツムリの歯舌を見たぐらいですかね。
というのは、冷凍庫にサンプルがたまってきたので
整理がてら標本をつくっておこうということになり、
凍ったカタツムリ(今回はアオミオカタニシとオキナワヤマタニシ)を
水酸化ナトリウムでグツグツ煮るのです。
そしたら歯舌が取り出せるってわけです。
んまぁ、そんなことをして
今後の活動(研究)をどーするか話して終了。という感じ。
はぁ、さっきまでボロクソな研究してヒーヒーしてたボクが研究を指導する立場なんて。。。
がんばろ。
さて、
以前、私が海岸を攻めまくってたときの写真がありましたので
それをポロリしちゃいます。
時期としては3月後半から4月にかけてぐらいですかねえ。
場所は本島南部というぐらいだけ。
ハマヒルガオですよ。

何か、あんましいないんですよね。そこまで群生するわけでもなし、ポチョポチョっと
咲いてるので見つけたらテンションあがっちゃう感じの花です。
ジシバリ。

走出枝(そうしゅつし)と呼ばれる茎を地面にはわせて増えていくタイプのやつです。
同じ茎から出ているやつらは遺伝的に同じ形質、つまりクローンをつくりながら増えていくのです。
アメリカハマグルマとかもそういう感じですよね。
茎が地面をはっている様子が地面を縛って見えるので、地縛り(じしばり)だそうですよ。
ハマダイゲキ。


中国に戟(げき)っていう武器があるんですけど、葉の付き方などがそれに似ていて
戟でも大きい戟に似ているからダイゲキ。
ちなみに戟はコレ↓↓

ちょっぴ似てますね。
(「China ARACHINA」より引用。URL「http://www.arachina.com/culture/bujyutu/bingqi.htm」)
これはイワダイゲキ。

名前の由来は同じです。こいつは浜にいなくて、岩にいるのでイワダイゲキ。
シマアザミ。海岸沿いでトゲトゲしている歯を付けます。

花を真正面(?)からまじまじと見るとなんか変な感じ。
キクの仲間は頭状花って言って、花びらに見える一つ一つが1つの花なんです。
私たちが普段目にして花だと思っているのは、花の集合体(頭状花)なんですわ。
そんで、この頭状花をじーっと見てると、外側の花の先端がもしゃもしゃしてるので
なにかなっと見ると

たぶん、花粉ですかね。そんな感じですね。
僕のもってるカメラじゃピント合わせるのこれが限界っす。ちくしょう。
海岸は光が直で当たるため、気温は森などに比べるとかなり高くなります。
なので、海岸の植生は割と冬~春ぐらいにかけて花を咲かせたり、
繁茂したりする奴らが結構います。夏はさすがに暑すぎるんでしょうね。笑
でも、まだ本格的に暑くなる前なので、海岸植生も結構にぎわってます。
たぶん。きっと。
海岸を散歩がてら植物観察はいかがでしょう。
沖縄生物教育研究会編の
「フィールドガイド 沖縄の生きものたち」
という本(2000円)もって歩けば、ある程度は分かると思います。
この本は、あんまり色んな書店ではみないのですが、
ジュンク堂には確実に売ってます。
なんか、宣伝みたいなことをしてしまった。笑
まぁ、手元に図鑑があるともっと楽しめるということっす。
それではまた。
このところ毎日更新でございます。
結構、頭の整理になったり、休憩になったりして良いかも。
っとこんな忙しい時期になって思います。
こんなことやってるヒマあったら単語の一つでも覚えろと
誰かに言われないかとビクビクしている今日この頃。
どうも僕です。
んー、今日は特に珍しいことはなく。
某学校の生物部の子たちとカタツムリの歯舌を見たぐらいですかね。
というのは、冷凍庫にサンプルがたまってきたので
整理がてら標本をつくっておこうということになり、
凍ったカタツムリ(今回はアオミオカタニシとオキナワヤマタニシ)を
水酸化ナトリウムでグツグツ煮るのです。
そしたら歯舌が取り出せるってわけです。
んまぁ、そんなことをして
今後の活動(研究)をどーするか話して終了。という感じ。
はぁ、さっきまでボロクソな研究してヒーヒーしてたボクが研究を指導する立場なんて。。。
がんばろ。
さて、
以前、私が海岸を攻めまくってたときの写真がありましたので
それをポロリしちゃいます。
時期としては3月後半から4月にかけてぐらいですかねえ。
場所は本島南部というぐらいだけ。
ハマヒルガオですよ。

何か、あんましいないんですよね。そこまで群生するわけでもなし、ポチョポチョっと
咲いてるので見つけたらテンションあがっちゃう感じの花です。
ジシバリ。

走出枝(そうしゅつし)と呼ばれる茎を地面にはわせて増えていくタイプのやつです。
同じ茎から出ているやつらは遺伝的に同じ形質、つまりクローンをつくりながら増えていくのです。
アメリカハマグルマとかもそういう感じですよね。
茎が地面をはっている様子が地面を縛って見えるので、地縛り(じしばり)だそうですよ。
ハマダイゲキ。


中国に戟(げき)っていう武器があるんですけど、葉の付き方などがそれに似ていて
戟でも大きい戟に似ているからダイゲキ。
ちなみに戟はコレ↓↓

ちょっぴ似てますね。
(「China ARACHINA」より引用。URL「http://www.arachina.com/culture/bujyutu/bingqi.htm」)
これはイワダイゲキ。

名前の由来は同じです。こいつは浜にいなくて、岩にいるのでイワダイゲキ。
シマアザミ。海岸沿いでトゲトゲしている歯を付けます。

花を真正面(?)からまじまじと見るとなんか変な感じ。
キクの仲間は頭状花って言って、花びらに見える一つ一つが1つの花なんです。
私たちが普段目にして花だと思っているのは、花の集合体(頭状花)なんですわ。
そんで、この頭状花をじーっと見てると、外側の花の先端がもしゃもしゃしてるので
なにかなっと見ると

たぶん、花粉ですかね。そんな感じですね。
僕のもってるカメラじゃピント合わせるのこれが限界っす。ちくしょう。
海岸は光が直で当たるため、気温は森などに比べるとかなり高くなります。
なので、海岸の植生は割と冬~春ぐらいにかけて花を咲かせたり、
繁茂したりする奴らが結構います。夏はさすがに暑すぎるんでしょうね。笑
でも、まだ本格的に暑くなる前なので、海岸植生も結構にぎわってます。
たぶん。きっと。
海岸を散歩がてら植物観察はいかがでしょう。
沖縄生物教育研究会編の
「フィールドガイド 沖縄の生きものたち」
という本(2000円)もって歩けば、ある程度は分かると思います。
この本は、あんまり色んな書店ではみないのですが、
ジュンク堂には確実に売ってます。
なんか、宣伝みたいなことをしてしまった。笑
まぁ、手元に図鑑があるともっと楽しめるということっす。
それではまた。
Posted by Cinnamomum_mk at 00:12│Comments(0)
│植物